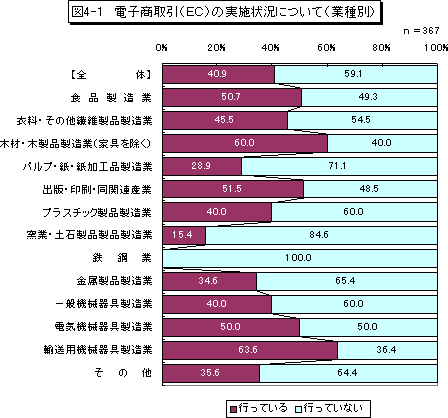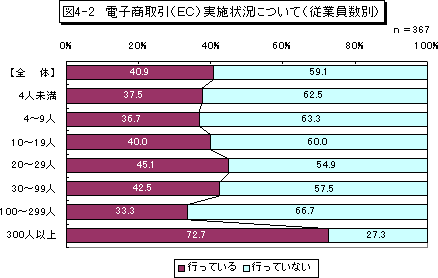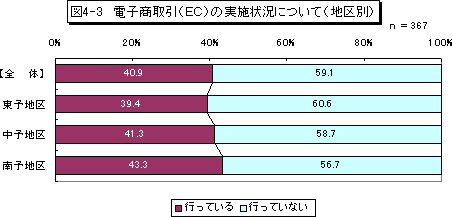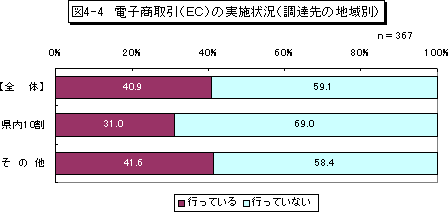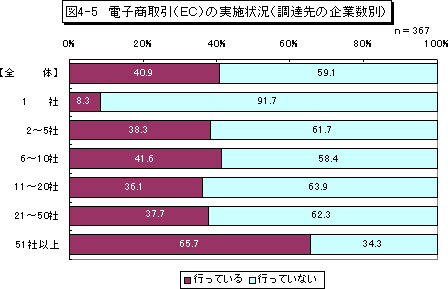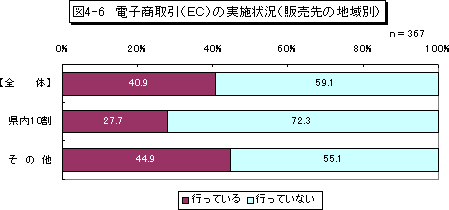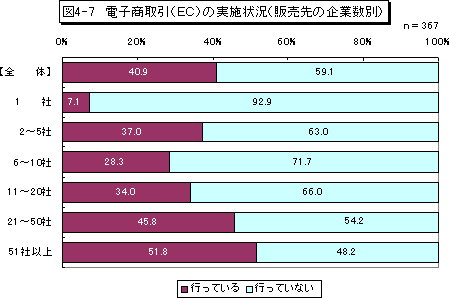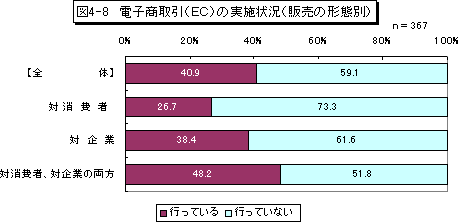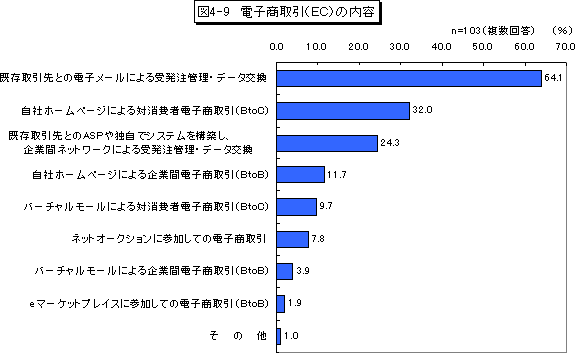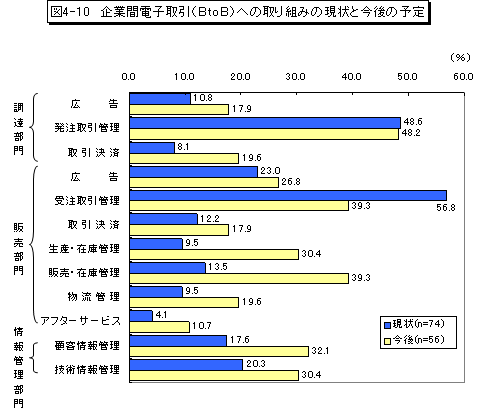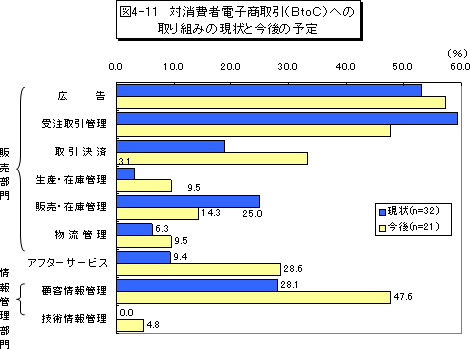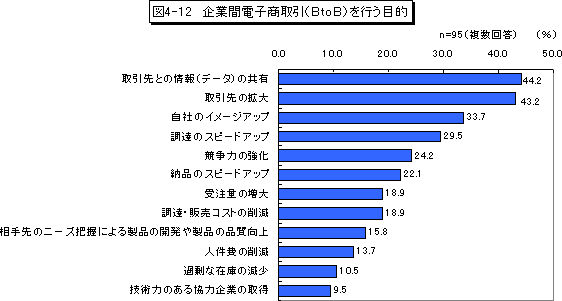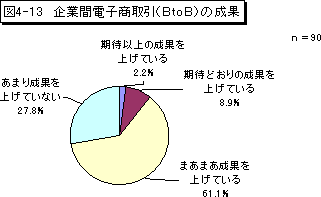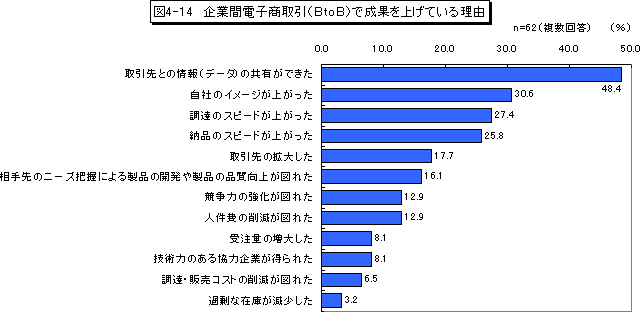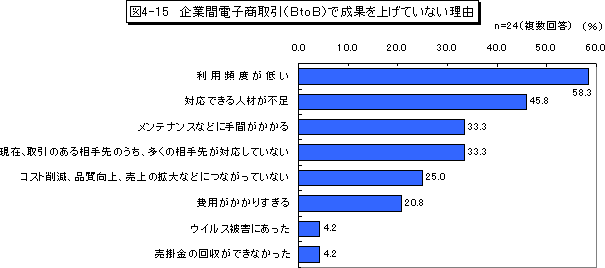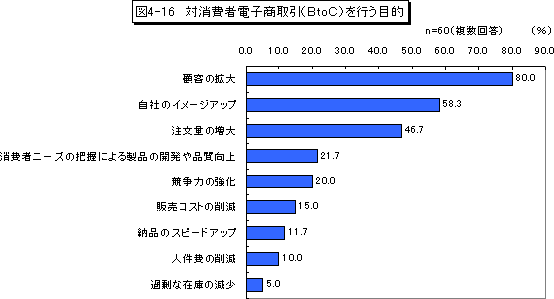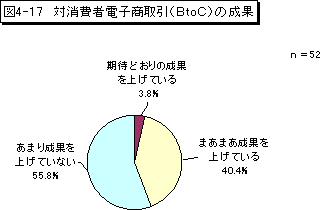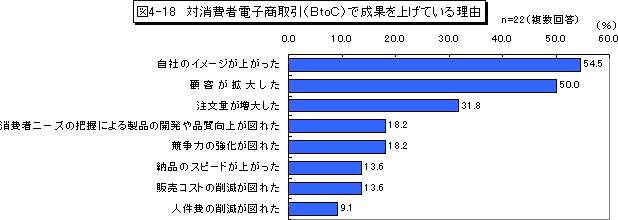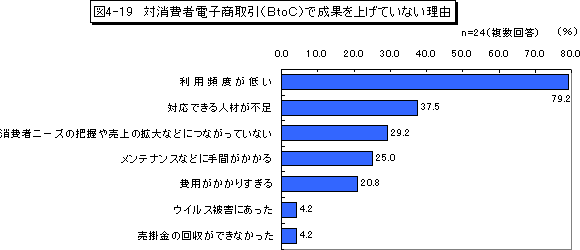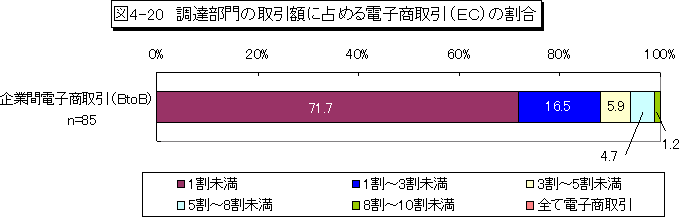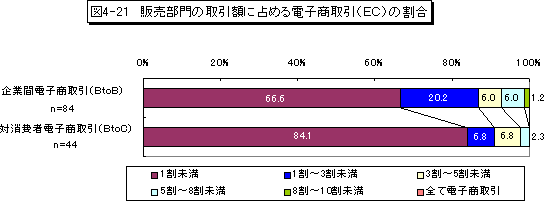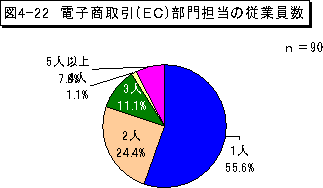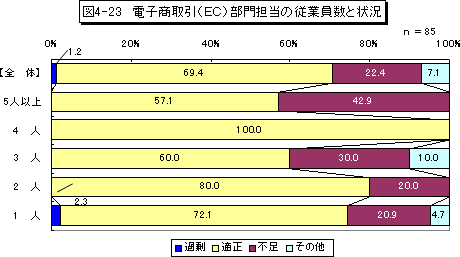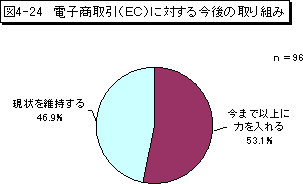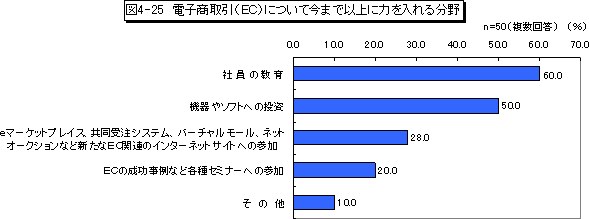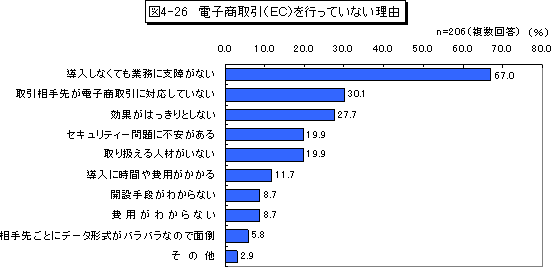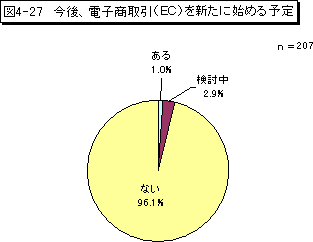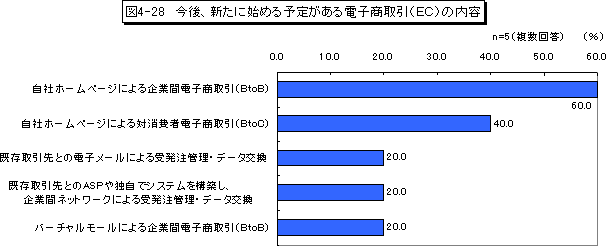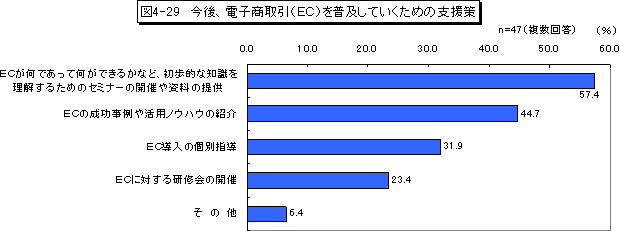6.インターネットを活用した電子商取引(EC)の実施状況について
電子商取引(EC)とは、パソコンを使ってインターネットなどのネットワークを経由した商取引のことである。企業と企業との間の電子商取引を「BtoB」(Business
to Business)、企業と個人間の電子商取引を「BtoC」(Business to Consumer)と言う。
なお、電子メールによる受発注管理やデータ交換、受発注先との設計・デザイン等のデータ交換も含まれる。 |
(1) 電子商取引(EC)の実施状況について
A.業種別
 |
コンピュータを導入しており、インターネットに接続している事業所に対し、電子商取引(EC)の実施状況を尋ねたところ、「行っている」が40.9%、「行っていない」が59.1%となっている(図4-1)。
業種別に見てみると、「輸送用機械器具製造業」が63.6%で最も多く、次いで、「木材・木製品製造業(家具を除く)」が60.0%、「出版・印刷・同関連産業」が51.5%となっている。また、コンピュータを導入しており、インターネットを接続している事業所が100%であった「電気機械器具製造業」では、電子商取引(EC)の実施率が50.0%に止まった。 |
B.従業員数別
 |
従業員数別に見てみると、電子商取引(EC)を行っていない事業所は、「4人未満」が62.5%、「4〜9人」が63.3%、「10〜19人」が60.0%、「20〜29人」54.9%、「30〜99人」が57.5%、「100〜299人」が66.7%となっている(図4-2)。
一方、「300人以上」では27.3%となっており、それ以外の事業所と比べて電子商取引(EC)を「行っている」としたものが多い。
このように、「300人以上」を別にすると、従業員数の規模での差はあまりみられなかった。 |
C.地区別
 |
地区別に見てみると、県内3地区とも電子商取引(EC)「行っていない」が60%前後となっており、電子商取引(EC)への取り組みについては、県内全体がほぼ同じ水準である(図4-3)。 |
D.調達先別
 |
調達先の地域別にみてみると、調達先が「県内10割」である事業所の取り組みが31.0%、県外にも調達先をもつ事業所の取り組みが41.6%となっており、コンピュータの導入状況やインターネットの接続状況のような大きな差はないが、広く調達先を求める割合は電子商取引(EC)が有効かつ必要であることがうかがえる(図4-4)。 |
 |
調達先の企業数別でみてみると、電子商取引(EC)を行っている事業所は、調達先企業数が「51社以上」が65.7%となっている。一方、「1社」では8.3%と大きな差があり、取引先企業数が多い事業所では、その必要性が高いことがうかがえる(図4-5)。 |
E.販売先別
 |
販売先別にみてみると、調達先が「県内10割」である事業所の取り組みが27.2%、県外にも調達先をもつ事業所の取り組みが44.9%となっており、調達の場合と同様に広く販売先を求めるには電子商取引(EC)が有効かつ必要であることがうかがえる(図4-6)。 |
 |
販売先の企業数別でみてみると、取引先企業数が多くなるほど電子商取引(EC)に取り組んでいる(図4-7)。 |
F.販売対象別
 |
販売の対象別にみてみると、コンピュータの導入状況やインターネットの接続状況と同様に、「対消費者」よりも「対企業」で電子商取引(EC)の必要性が高いと思われる(図4-8)。 |
(2)
電子商取引(EC)の取組内容
A.電子商取引(EC)の内容
 |
電子商取引(EC)を「行っている」と答えた事業所に対し、その取組内容を尋ねたところ、「既存取引先との電子メールによる受発注管理・データ交換」が64.1%と最も多く、次いで「自社ホームページによる対消費者電子商取引(BtoC)」」が32.0%、「既存取引先とのASPや独自でシステムを構築し、企業間ネットワークによる受発注管理・データ交換」が24.3%となっており、一方、「自社のホームページによる企業間電子商取引(BtoB)」以下については現在、取り組みが少ないが、今後、開拓し得る取り組み分野であるともいえる。 |
B.企業間電子商取引(BtoB)
 |
企業間電子商取引(BtoB)の内容について、現在の取組状況と今後の取組予定とをみてみると、調達部門では、現状および今後の取組予定ともに「発注取引管理」が多くなっており、販売部門でも現状および今後の取組予定ともに「受注取引管理」が多くなっていることから、企業間電子商取引(BtoB)においては、電子商取引(EC)の受発注管理における活用ニーズが高いことがうかがえる。
また、今後の取組予定については、「各項目に取り組みたい」との回答が出ており、電子商取引(EC)をより広い分野で活用しようという意欲がうかがえる(図4-10)。 |
C.対消費者電子商取引(BtoC)
 |
対消費者電子商取引(BtoC)について、現在の取組状況と今後の取組予定とをみてみると、「販売部門」では、現状および今後の予定ともに「広告」、「受注取引管理」が多くなっており、「情報管理部門」では「顧客情報管理」が多くなっていることから、対消費者電子商取引(BtoC)においては電子商取引(EC)の「広告」、「受注取引管理」および「顧客情報管理」における活用ニーズが高いことがうかがえる(図4-11)。 |
(3)
企業間電子商取引(BtoB)の目的と成果
A.企業間電子商取引(BtoB)を行う目的
 |
企業間電子商取引(BtoB)を行う目的を尋ねたところ、「取引先との情報(データ)の共有」が44.2%と最も多く、次いで「取引先の拡大」が43.2%、「自社のイメージアップ」が33.7%、「調達のスピードアップ」が29.5%となっている(図4-12)。 |
B.企業間電子商取引(BtoB)の成果
 |
企業間電子商取引(BtoB)の成果を尋ねたところ、「期待以上の成果を上げている」が2.2%、「期待どおりの成果を上げている」が8.9%、「まあまあ成果を上げている」が61.1%となっており、合わせて72.2%の事業所が成果を上げている。(図4-13)。
企業間電子商取引(BtoB)では、取引先の拡大を除き固定された取引先が多く、取引関係が安定していることから、投資に見合った成果が得られていることが推測される。 |
C.企業間電子商取引(BtoB)で成果を上げている理由
 |
企業間電子商取引(BtoB)で成果を上げている理由を尋ねたところ、「取引先との情報(データ)の共有ができた」が48.4%と最も多く、次いで「自社のイメージが上がった」が30.6%、「調達のスピードが上がった」が27.4%、「納品のスピードが上がった」が25.8%となっており、取引先との情報共有など企業間の連携に具体的な成果が表れていることがうかがえる(図4-14)。 |
D.企業間電子商取引(BtoB)で成果を上げていない理由
 |
企業間電子商取引(BtoB)で成果を上げていない理由を尋ねたところ、「利用頻度が低い」が58.3%と最も多く、次いで「対応できる人材が不足」が45.8%、「メンテナンスなどに手間がかかる」、「現在、取引のある相手先のうち、多くの相手先が対応していない」が33.3%となっており、今後は経営実態に合った企業間電子商取引(BtoB)の取組支援や人材育成支援が必要と考えられる(図4-15)。 |
(4)
対消費者電子商取引(BtoC)の目的と成果
A.対消費者電子商取引(BtoC)を行う目的
 |
対消費者電子商取引(BtoC)を行う目的を尋ねたところ、「顧客の拡大」が80.0%と圧倒的に多く、次いで「自社のイメージアップ」が58.3%、「注文量の増大」が46.7%となっている(図4-16)。 |
B.対消費者電子商取引(BtoC)の成果
 |
対消費者電子商取引(BtoC)の成果を尋ねたところ、「期待どおりの成果を上げている」が3.8%、「まあまあ成果を上げている」が40.4%となっている。このように、成果が上がっているとする割合は半数を下回っており、企業間電子商取引(BtoB)と比べて低い(図4-17)。 |
C.対消費者電子商取引(BtoC)で成果を上げている理由
 |
対消費者電子商取引(BtoC)で成果を上げている理由を尋ねたところ、「自社のイメージが上がった」が54.5%と最も多く、次いで「顧客が拡大した」が50.0%、「注文量が増大した」が31.8%となっており、イメージアップと販路拡大に成果が上がっている(図4-18)。 |
D.対消費者電子商取引(BtoC)で成果を上げていない理由
 |
対消費者電子商取引(BtoC)で成果を上げていない理由を尋ねたところ、「利用頻度が低い」が79.2%と最も多く、次いで「対応できる人材が不足」が37.5%となっており、1位、2位ともに企業間電子商取引(BtoB)の場合と同様の順位となっている(図4-19)。
また、3位は「消費者ニーズの把握や売上の拡大などにつながっていない」で29.2%となっているなど、対消費者電子商取引(BtoC)を導入したものの、成果を得られていない事業所も少なくないことから、IT化社会に即した経営戦略を立て直すとともに、消費者のニーズを択えた商品構成の見直しやホームページコンテンツの一層の充実を図るための支援が必要である。 |
(5)
取引額に占める電子商取引(EC)の割合
A.調達部門の取引額に占める割合
 |
直近の決算年度における調達部門の取引額に占める企業間電子商取引(BtoB)の割合を尋ねたところ、「1割未満」が71.7%と圧倒的に多く、次いで「1割〜3割未満」が16.5%、「3割〜5割未満」が5.9%となっている(図4-20)。
なお、「全て電子商取引」と答えた事業所はなかった。 |
B.販売部門の取引額に占める割合
 |
直近の決算年度における販売部門の取引額に占める企業間電子商取引(BtoB)と対消費者電子商取引(BtoC)の割合を尋ねた。
企業間電子商取引(BtoB)の割合を見てみると、「1割未満」が66.6%と最も多く、次いで「1割〜3割未満」が20.2%、「3割〜5割未満」と「5割〜8割未満」が6.0%となっている。
一方、対消費者電子商取引(BtoC)の割合を見てみると、「1割未満」が84.1%と圧倒的に多く、次いで「1割〜3割未満」と「3割〜5割未満」が6.8%となっている。
前問Aと同様、企業間電子商取引(BtoB)と対消費者電子商取引(BtoC)ともに「全て電子商取引」と答えた事業所は、なかった(図4-21)。
このように、電子商取引(EC)はその取引金額規模からすれば、調達部門、販売部門ともに十分活用されるまでには至っていない。
しかし、現状で取引金額規模は小さいが、IT化の進展により今後、伸びていくことが予想される。 |
(6) 電子商取引(EC)部門担当の従業員数と状況
 |
電子商取引(EC)部門を担当している従業員数を尋ねたところ、「1人」が55.6%で最も多く、次いで「2人」が24.4%、「3人」が11.1%、「5人以上」が7.8%となっている(図4-22)。 |
 |
さらに、その状況を尋ねたところ、電子商取引(EC)部門の担当者が「5人以上」と答えた事業所では、42.9%が「不足」しているとしており、積極的に電子商取引(EC)を利用している事業所では、電子商取引(EC)部門の担当者を確保する必要性を感じているようだ(図4-23)。
また、「その他」の中には、兼務することなどにより、概ね適正人員を確保しているとの回答もあった。 |
(7) 電子商取引(EC)に対する今後の取り組み
A.電子商取引(EC)に対する今後の取り組み
 |
電子商取引(EC)に対する今後の取り組みを尋ねたところ、「今まで以上に力を入れる」が53.1%と最も多く、「現状を維持する」が46.9%であったが、「縮小する」や「ECをやめる」と答えた事業所は、全くなかった。このようなことからも、電子商取引(EC)は、企業経営にとって重要な存在になってきていることがうかがえることから、一層の支援が必要と考えられる(図4-24)。 |
B.電子商取引(EC)について今まで以上に力を入れる分野
 |
前問Aで「今まで以上に力を入れる」と答えた事業所に、今まで以上に力を入れていきたい分野を尋ねたところ、「社員の教育」が60.0%で最も多く、次いで「機器やソフトへの投資」が50.0%、「eマーケットプレイス、共同受注システム、バーチャルモール、ネットオークションなど新たなEC関連のインターネットサイトへの参加」が28.0%となっている(図4-25)。
人材育成やIT環境(ハード、ソフト)への投資など、電子商取引(EC)対応力を一層高めていきたいという意欲がうかがえる。
また、「その他」の中には、「消費者が欲しがるような特色のある製品を作りたい」という電子商取引(EC)を意識した新製品開発について、前向きな意見も見られた。 |
(8) 電子商取引(EC)を行っていない事業所の状況
A.電子商取引(EC)を行っていない理由
 |
電子商取引(EC)を行っていない事業所に、その理由を尋ねたところ、「導入しなくても業務に支障がない」が67.0%で最も多く、次いで「取引相手先が電子商取引に対応していない」が30.1%、「効果がはっきりとしない」が27.7%となっている(図4-26)。 |
B.今後、電子商取引(EC)を新たに始める予定について
 |
電子商取引(EC)を行っていない事業所に対し、今後、電子商取引(EC)を新たに始める予定について尋ねたところ、「ある」が1.0%、「検討中」が2.9%に止まった。一方で、「ない」は96.1%と多数に上っており、電子商取引(EC)を行う事業所と行わない事業所の二極分化が進んでいることがうかがえる(図4-27)。 |
C.今後、新たに始める予定がある電子商取引(EC)の内容
 |
前問Bで、今後、新たに電子商取引(EC)を始める予定が「ある」または「検討中」と答えた事業所に対し、その内容を尋ねたところ、「自社ホームページによる企業間電子商取引(BtoB)」が60.0%で最も多く、次いで「自社ホームページによる対消費者電子商取引(BtoC)」が40.0%となっている(図4-28)。 |
D.今後、電子商取引(EC)を普及していくための支援策
 |
電子商取引(EC)を行っていない事業所に対し、今後、電子商取引(EC)を普及するための支援策について尋ねたところ、「ECが何であって何ができるかなど、初歩的な知識を理解するためのセミナーの開催や資料の提供」が57.4%と最も多く、次いで「ECの成功事例や活用ノウハウの紹介」が44.7%、「EC導入の個別指導」が31.9%となっており、今後、電子商取引(EC)を普及していくためには、入門的な内容を中心とした支援策が求められている(図4-29)。 |
|